国際協力の仕事
―パレスチナ、ベトナムの教師との共同から学んだこと
津久井 純 (国際開発センター・主任研究員)
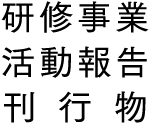
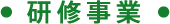
高等教育推進機構国際教育研究部では、大学教員の教育研究能力を高め、学内外の交流を深めることを目的に、年に数回(不定期)の研修会を開催しています。本研修会では、「日本語・日本語教育」「多文化交流科目」「国際教育」をキーワードに、本組織が現在取り組んでいる教育研究に関わるさまざまな最新の理論と実践を紹介しています。
学内外を問わずどなたでも参加できますので、ご興味のある方は、その都度更新される開催案内を参考にして、ふるってご参加ください。
2025年3月18日(火)
講演会+ミニワークショップ
「言語・異文化間教育とナラティヴー理論と実践ー」
北出 慶子氏 (立命館大学 文学部言語コミュニケーション学域・教授)
2025年2月8日(土)
科研費(20K02931)研究成果報告会
「韓国・日本の大学における『合理的配慮』をめぐる支援の動向
鄭 惠先氏 (北海道大学高等 教育推進機構・教授)
趙 宣映氏 (韓国仁川大学 日語教育科・教授)
榊原 佐和子氏 (北海道大学学生相談総合センター・准教授)
2025年2月1日(土)
多文化協同学習における学生ファシリテーターを育成する
ー東北大学国際共修サポーターを事例としてー
米澤 由香子氏 (東北大学・准教授)
秋庭 裕子氏 (東京学芸大学・准教授)
2025年1月25日(土)
「北海道 ナゼここに? 新しいコミュニティ」
宮入 隆氏 (北海学園大学経済学部・教授)
深江 新太郎氏 (NPO多文化共生プロジェクト・代表)
水田 充彦氏 (キャリアバンク株式会社海外事業部・部長)
栗田 知宏氏 (東京外国語大学南アジア研究センター・特定研究員)
澤田 彰宏氏 (東京外国語大学・非常勤講師)
長崎 哲之氏 (浦河町役場企画課・課長)
稲岡 千春氏 (浦河町地域おこし協力隊)
土門 寛治氏 (北海道新聞社・記者)
林 佑樹氏 (すずかぜ合同事務所・行政書士)
ソバン ファルーク氏 (北海道情報大学・学部1年生)
2024年9月27日(金)
講演会(オンラインZOOM開催)
「移民教員の活用による教員不足の解消と労働力の多様化」
Dr Sun Yee Yip (Monash University, Australia)
齊藤 英介氏(モナシュ大学・オーストラリア)
2024年9月5日(木)
対面ワークショップ 日本語教育に関わるわたしたちのキャリア
ーこれまでを振り返り、これからを考えるー
山本 晋也 氏(周南公立⼤学・准教授)
松尾 憲暁 氏(岐阜大学・助教)
近藤 弘 氏(北海道大学・講師)
2024年1月27日(土)
まるごと北海道+沖縄 わいわい考える多文化共生のイマ
幅口 一路氏(北海道総合政策部国際局国際課・課長補佐)
北河 実則氏(外国人技能実習機構札幌事務所・所長)
池田 誠氏(一般社団法人 北海道国際交流センター・専務理事/事務局長)
尾上 健介氏(社会福祉法人さつき会法人本部地域密着型サービス事業部・部長)
久保田 一完氏(Unite Works・代表/株式会社スマヒロ・インターナショナル
リクルーティングアドバイザー)
武田 昌之氏(株式会社URコミュニティ北海道住まいセンターお客様相談課)
松田 麻美氏(モンテカルロ商事株式会社)
宮城 潤氏(若狭公民館・館長)
神吉 宇一氏(武蔵野大学・教授)
2023年11月5日 (日)
文化のもつ「具体的」な意味ー間接的コミュニケーションをめぐってー
弘田 陽介氏(大阪公立大学・教授)
「話し合い」を考えよう
2023年8月19日 (土)
村田 和代氏(龍谷大学・教授)
水上 悦雄氏(情報通信研究機構)
森本 郁代氏(関西学院大学・教授)
2023年7月16日 (日)
外国につながる子ども・家族を支える地域日本語教室~「ことば」の支援を越えて~
伊藤 亜希子氏(福岡大学・教授)

高等教育推進機構国際教育研究部では、外国人留学生・研究生らに対する日本語科目と、留学生と日本人学生がともに日本語で学ぶ「多文化交流科目」を提供しています。各授業の様子や学生の成果物等をご紹介します。ぜひご覧ください。

高等教育推進機構国際教育研究部では、毎年定期的に発行される紀要をはじめ、「北海道大学日本語スタンダーズ」「多文化交流科目」ブックレットシリーズなどの印刷物を通して、本組織が現在取り組んでいる教育研究について広く紹介、報告しています。リンク先から自由にダウンロードできますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。
【特集】
諸外国における「合理的配慮」の捉え方と大学における支援の取り組み : 関係者への聞き取り調査から見えること
Ⅰ. 研究の概要と本特集の校正 (青木麻衣子、鄭惠先)
Ⅱ. 西洋諸国の大学における合理的配慮を必要とする学生への支援と現状 (青木麻衣子)
Ⅲ. 韓国の障害関連法案と「合理的配慮」運用上の特徴:韓国の大学での聞き取り調査の結果をもとに (鄭惠先)
【研究論文】
学習者が日本語母語話者の非流暢性に見る「母語話者らしさ」とその運用意向 (佐藤淳子)
【調査報告】
北海道大学一般日本語初級コースの学習者アンケート調査報告 : コースデザインの見直しに向けて (杜長俊、近藤弘)
【特集】
演劇の手法を用いた共生のまちづくりの試み : 「多文化えんげきワークショップin EBETSU」の実践と住民間の話し合い分析
住民間の対等な話し合いの場の創出 : 演劇の手法を用いた話し合いのデザイン(平田 未季)
他者による感情カードの発見によって作られる発話順番 : 日本語母語話者と非母語話者による話し合い場面の事例分析から(山本 真理)
多文化の話し合いの「個人の経験を共有する活動」で目指される相互理解とは? : 感情に焦点を当てる仕掛けの効果をめぐって(杜 長俊)
【実践報告】
再話を用いた読解授業 : 学生評価を中心に(佐藤 淳子)
博士留学生を対象としたオンデマンド日本語コース「基礎日本語能力開発プログラム」(BJDP) : プログラム実施の背景と実施報告(山畑 倫志)
【調査報告】
日本語上級学習者の正確で潤沢な敬意表現使用はポライトネス評価につながったか(延与 由美子)
【特集】
実際の取り組みからみる北海道の地域日本語教育の現状
北海道日本語センターによる地域日本語教育の取り組み(二通 信子、阿部 仁美、大井 裕子)
自治体主導の地域日本語教室ができるまで : 北海道恵庭市における実践報告(式部 絢子)
地域の多文化共生推進に必要な連携とその課題 : 苫小牧市国際化推進事業における活動から(五十嵐 啓子)
国際交流団体による地域日本語教室の開設 : ハレの国際交流から日常の学習支援へ(平田 未季)
【実践報告】
意見述べ発話時の気づき支援は語彙的多様性に影響を与えるか : 中級クラスでの実践をもとに(佐藤 淳子)
【研究論文】
外国人留学生の「異文化間能力」に対する意識の形成プロセス : 質的分析を通して見える社会・文化的な相互作用(鄭 惠先、永岡 悦子)
【実践報告】
初級日本語クラスにおけるオンライン及びハイフレックス型授業実践 : 実用日本語クラスでの実践から(黄 美花、長谷川 洋枝、屋方 淳子、山本 さやか)
【調査報告】
日本語を母語としない保護者とのコミュニケーション : 北海道A保育園の調査から支援の在り方を考える(藤原 安佐)
【特集】
2020年度第1学期の北海道大学日本語コースにおけるオンライン授業報告(平田 未季)
まえがき : 2020年度日本語科目オンライン化の経緯とその課題(平田 未季)
YouTubeを使った動画配信型会話能力試験の試み PDF (鈴木 紀子)
非漢字圏出身者を対象とする初級漢字科目のオンライン授業実践報告 PDF (市川 明美)
同期型オンライン授業を用いた協働学習で学生は何を学んだか : 学生からの振り返りを中心に PDF (佐藤 淳子)
オンライン授業におけるビブリオバトルの試み : 中級日本語クラスでの実践から (山本 さやか)
2020年度「一般日本語コース」のオンライン授業に関するアンケートについて PDF (山畑 倫志)
【研究論文】
長谷川雄太郎研究・その4
―「日語入門」修正過程の分析に基づく考察―(中村 重穂)
【研究ノート】
「オーストラリアン・カリキュラム」を読む : 5年生の英語を事例として
(青木 麻衣子、浮田 真弓)